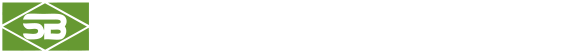建 具
建具とは
建具とは、入り口や窓など建物の開口部に
設けられるものの総称です。
ドアや扉、襖・障子、ガラス戸など可動するものが多く、特殊な例として欄間やFIX窓、掛け障子など
固定のものもあります。
キッチンの扉ハッチ、クローゼットの折れ戸なども建具。
一般的に木製が多く利用されていますが、
アルミサッシやスチールドアなど金属製も多々あります。
多くの方が知らず知らず日常的に
ご利用されるのが、建具です。
白石物産の建具
当社は昭和2年に木材店として開業し、戦中の混乱期を経て戦後再開以来70有余年様々な建具を提供してまいりました。
一般住宅はもちろん、公共施設や商業施設、集合住宅など関東を中心に各地でご利用頂いております。

飲食店 店舗入口 地桧白材 引き分け格子戸
寒冷地のため風除室設置例
公共施設 分庁舎ロビー WOOD INFILL
県産杉集成材・伝統工芸品 真岡木綿とのコラボ
マンション エントランス オーク材 引き分け一枚ガラス戸 
和風住宅 廊下廻り 地杉赤材大阪格子戸 
オフィス 受付カウンター 応接室 WOOD INFILLを利用し、地杉鹿沼組子のパーティションと腰付きガラス戸を使用 
和風住宅 地杉赤材 大阪格子戸 内観(格子両面仕様) 
和風住宅 地杉材 無双付き上げ下げ障子 
住宅 米松材 一枚ガラス木製サッシ戸 
住宅 間仕切開閉折戸 布クロス地入り腰付きガラス戸(フラッシュ芯組) 
店舗入り口 米松材 腰付き一枚ガラス 親子ドア 
住宅 和室 柳収まり 地杉白材狐格子戸 
住宅 クローゼット入口 地杉白材縁 和襖
木工建具のまち鹿沼
関東の北部、栃木県中西部に位置する鹿沼市。良質な杉や桧など木材資源に恵まれたこの土地の、木工の歴史は約400年前にさかのぼります。
寛永13年(1636年)日光東照宮造営の折り、各地から腕利きの宮大工や職人が集結。
日光からほど近く、木材集散地となる平坦な土地を持つ鹿沼市に、逗留・永住した彼らがその技術を伝承したのが起こりとされています。
あらゆる装飾技法を駆使して造られた絢爛豪華な日光東照宮。文政元年(1818年)の日光五重塔再建時に、彫物大工の棟梁を務めた後藤周二正秀は、天保7年(1836年)に中町(現:鹿沼市仲町)の彫刻屋台を製作しました。この頃は老中水野忠邦により天保の改革がなされた時期で、祭りの際の踊りや芝居、華美はすべて禁止。移動舞台としての機能を持った屋台は彫刻屋台となり、町内で競い合うように壮麗な彫刻屋台を作るようになりました。建具、組子、彫刻といった彫刻屋台に息づく職人の精緻な技。
それが今の技術力の基準となっているのです。その後、関東大震災や戦災からの復興で鹿沼建具は大きく飛躍。時代のニーズにあわせ、産業は変遷をたどりながら、鹿沼市は日本屈指の木工建具産地へと発展を遂げました。豊富な木材、優れた製材業者、卓越した職人と近代的な機械設備、木工に関する様々な専門業者を有し、首都圏からのアクセスの良さを活かして構築させた流通体制。あらゆる要望に対応し、しっかりと答えていく。
木と共存する未来のために、鹿沼の木工はたゆみなく歩み続けます。

鹿沼組子
組子は、古来より欄間、書院障子などに用いられ、その他にも板戸やガラス戸、障子など、和室の建具を飾る最高の贅沢品とされてきました。
鹿沼組子は、最高級材の木曽桧や地元の日光杉の柾目の細かい部分を使用しています。釘や金具などをいっさい使わず、何千もの部品に切り込みを入れて手作業で組んでいきます。その正確な組み込みは非常に繊細で神経を使う作業であり、熟練の組子職人だけが作れる貴重な伝統技術です。しかし近年、日本家屋を建築する需要も少なくなり、和室そのものが減少し、その技法を受け継いでいくことも難しくなってきました。鹿沼組子の施された製品は、栃木県からは「栃木県伝統工芸品」、鹿沼市からは「かぬまブランド」の指定を受けています。現在では、和室に限らずホテルのロビーや美術館のエントランス、TVスタジオのディスプレイ、公共建築物など幅広い空間に採用され、インテリアとしても利用されています。世界中で日本の文化や伝統、技術・製品がクールジャパンと称され注目を浴びる中で、鹿沼組子も日本の技術を象徴する伝統工芸品として注目されつつあります。
組子とは
組子は、細く薄い組手と呼ばれる棒状の部材を、釘を使わず手作業で様々な模様を組み合わせていく技法のことを指し、組み上がった作品も「組子」と表現します。
組子の種類について
現在でも新しいデザインが生まれておりますが、基本の形を「地組」といい、中に入れる部材を「葉」と呼びます。
「地組基本形=枡組(角物)・菱物・亀甲物・三ツ組手」など葉の入れ方により組子は様々な表情を浮かべ、同じ形状を二重三重と入れる事で緻密な組子が生まれます。
麻の葉模様
麻は、縄文時代から織物や縄などに使われていました。三ヶ月で2メートル以上にも伸び、その繊維が強いことから、スクスクと真っ直ぐに強く育ってほしいと願う親の気持ちを込めて、赤ん坊の産着には『麻の葉模様』の付いたものを着せる習慣がありました。
また、麻は神聖な植物とされ、【魔を除ける呪力がある】とも言われています。日本での麻の生産は、現在では極わずかとなりその殆どが、鹿沼市の北西部での栽培品となっています。組子の麻の葉模様は、まず桟に切り込みを入れて三本の桟を平らに組み合わせ、三ツ組手(みつくで)地組と言われる三角形の幾何学模様を作ります。三角形の中に、手作業でより細かい桟を加工して組み込み、麻の葉模様を作ります。